|
|
03-03
中仙水の郷まちぐるり博物館・黒塀条例 |
Nakasen Town Water Scape Featuring,
Walk Around Museum,
Kurobei Black Fence Rennovation |
|
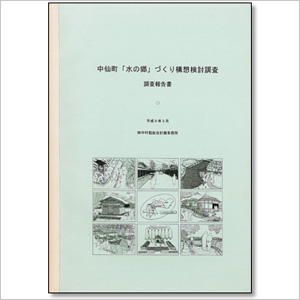 |
| 秋田県大仙市中仙 |
| 2002年 |
| 歴史を軸としたまちづくり |
|
|
■中仙町は水の美しいまちである。水面と地面が近く、豊富な水量の川や用水が多い。当初、県立公園の集会場や資料館の計画で県から推薦されて伺ったが、そのうちその景色の美しさと水の魅力にひかれ、水の郷の調査を委託された。
■秋田大学の学長を務めた神野先生に導かれ、清原氏が仙北平野の南の金沢から起こったこと、鉱物をめぐって俘囚の長となり、岩手青森の安部貞任と権力を争う、前九年、後三年の役の舞台だったこと、中央政府から藤原朝の平泉への文物の流通は、太平洋でなく、日本海廻船を通って、雄物川舟運に乗り換え、羽後長野まで来たこと。そこから陸路東へ、奥羽山脈を越えるルートがあったことなどを解明していった。
■玉川が玉川温泉によって酸性度が高く、一度田沢湖に導入してから田沢湖用水として開拓が1661年以降に始まった。その後7期にわたり、東に用水開拓は発展し、現在は奥羽山脈の西を走っている。この江戸時代の用水開拓により、東から西への川と北から南への用水が立体的に交差しながら縦横に森を切り開き、水田開発を進めてきた。その結果として現在の風景が作られた。
■奥羽山脈から40年の伏流水が玉川の東で湧水となり、天王清水などの神社を中心とした散居の集落が生まれ、それが北陸の砺波平野に匹敵する美しい散居風景のもととなっている。
■羽後長野で陸揚げされた文物は、御役屋で課税され、その後市中に流れ、二日市、六日市、九日市などの市内数か所で開かれる市場で売り買いされた。このうちの代表的な二日市の街並みが鈴木酒造(秀吉)に残る、黒塀であった。残存する黒塀のスタイルを調査し、これを復活する町条例を議会で可決してもらい、2.5万円/mの補助金を出して復活する活動を始めた。県議の大野氏がさっそくコンクリートブロック塀を美しい白壁のある黒塀に改造した。
■それに前後し、旧集会場の跡地を利用した公園の設計を委託された。道路沿いの用水と下段の用水をつなぐ、雁行の水路を引き、下段用水中央に四角い浅い池を掘り、中央に陰をつくる水の家とベンチを設けた。
WORKS:水の公園(二日町公園)
|
|
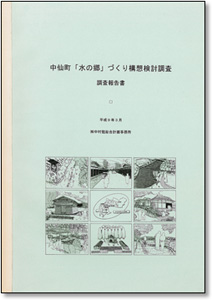
中仙町「水の郷」づくり構想検討調査
調査報告書(抜粋)(PDF:6.19MB)
|
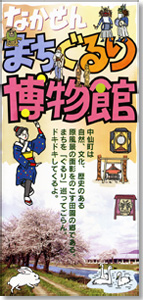
なかせんまちぐるり博物館パンフレット(PDF:4.00MB)
|
|